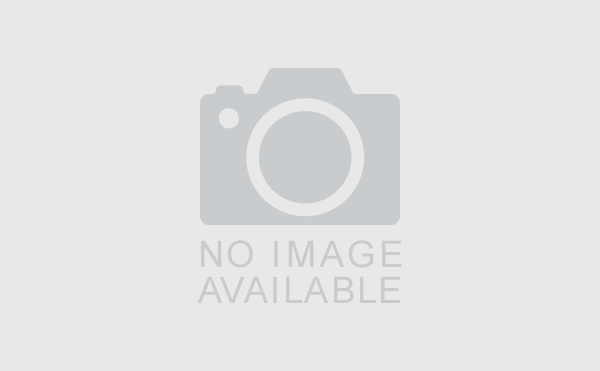営業所
営業所とは、本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう(令1条)。本店、支店は常時建設工事の請負契約を締結していないとしても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものであれば営業所に該当する。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、協議の契約締結等請負契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問わない(事務ガイドライン【第3条関係】2)。
申請実務においては、営業所としての要件を備えているか否かの確認事項として、下記7点の事項について留意されたい。
①外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
②固定電話、机、各種事務台帳を備えていること
③契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
④事務所としての使用権原を有していること
⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること、
等が判断要素になり、さらに後述する許可要件に関わる
⑥経営業務の管理責任者又は令3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者) が常勤していること
⑦専任技術者が常勤していること
を満たす必要がある。これらは、写真や平面図等の提出や、場合によっては立入調査を行うことによって確認される。
処分事例
有限会社Iの営業所の所在地が確知できないため、平成29年9月28日付長野県報でその旨を公告したが、公告後30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。このことは法29条の2第1項に該当し、許可の取り消し処分とする(2017年11月13日長野県知事)
営業所と軽微な建設工事
「営業所」と軽微な建設工事の関係について、深く掘り下げていきたい。
例えば、東京都が本店で埼玉県と神奈川県に支店がある業者において、これまで本店・支店が軽微な建設工事(内装)のみを請け負っていたとする。この業者が東京本店を主たる営業所として内装工事業の許可を取得したが、埼玉県と神奈川県においては、専任技術者を営業所に専任させることができず、「営業所」として申請できなかった。この場合、埼玉支店と神奈川支店では、建設業許可を取得できないため、建設工事の請負契約を締結することはできない。
では、軽微な建設工事の請け負う場合はどうか。軽微な建設工事であれば、許可の取得は不要であるため、問題なく請け負うことができそうだが、国土交通省はこれを明確に否定している。
すなわち、国土交通省は、建設業許可を取得した建設業者の「営業所」を、当該許可を取得した営業所だけでなく、当該建設業者が取得した当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。
したがって、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては、当該業種について営業することはできないこととなる(事務ガイドライン【第3条関係】2)。
許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ行う営業所についても、法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可が必要であるものとして取り扱う(事務ガイドライン【第3条関係】1(1))。
冒頭の例に戻って考えると、この業者は、埼玉県と神奈川県の支店では軽微な建設工事(内装)ですら請け負うことはできない。各支店で請け負うことができるようにするには、大臣許可を取得する(許可換え新規申請:現在有効な許可を受けている行政庁から有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に申請する場合)必要がある。もっとも大臣許可を取得するということは、営業所ごとに専任技術者を専任させるだけの技術者確保が必要であるため、当然に許可取得のハードルは高くなる。
「許可を取ったら仕事が増える」ことが一般的であるが、その例外が当該事例といえよう。許可を取ることで、支店は身動きが取れなくなる。会社の成長過程において、技術者の養成・確保と許可取得管理をバランスよく行うためには、定期的な社内分析と中長期の成長計画の策定が必要であるといえる。